大嶺の『地バーリー』(那覇市無形民俗文化財)

ハーリーといえば、海神祭。海に爬龍船やサバニを浮かべて、御願バーリーやハーリースーブ(競漕)をしている光景を思い浮かべるのですが、小禄の大嶺は陸地でハーリー儀式を行うのです。
『大嶺の地バーリー(ぢばーりー)』は、平成13年10月1日に那覇市無形民俗文化財に指定された字大嶺の伝統行事。

(♪『大嶺の地バーリー』のハーリー唄はこちらクリックして試聴できます)
『地バーリー』といえば、那覇ハーリーで知られる“泊”の地バーリーを思い浮かべるかもしれませんが生い立ちは違います。
そもそも那覇は商業のまち。那覇ハーリーでは“久米”などの漕ぎ手として、大嶺(ウフンミー)の海人が参加していたほど。もちろん、字大嶺でもいつの頃からかハーリーが行われていたといいます。
大嶺岬の浜は遠浅で、干潮時にはかなり沖のほうまで漕いで行かなくてはならなかったようです。その距離、1キロはあったのではないかという話も。
そこで字民のために、前の浜(メーヌハマ)まで船を担いできて、船を漕ぐ姿をみせたのがはじまりだといわれます。
また、ある年には集落内に伝染病(フーチ)がはやり、那覇ハーリーを応援に行けなくなったので、その浜で再現したものだという言い伝えもあるようです。

さて、この大嶺の『地バーリー』ですが、地域の先輩方からの言い伝えでは、その年代についてはいくつかの説があるようですが、文献として記録に残っていて確認がとれるものが明治19年頃ということで“その頃から”ということで統一することにはなったらしいのです。
ところが一説には、その歴史は糸満ハーレーよりも古いとされる説もあるようです。

どれくらい古いのかというと、そもそもハーリーの爬龍船などは中国から渡ってきたともいわれますが、海を渡ってきた際、一緒に土地の神・農耕の神である“土帝君”も小禄に渡ってきたといいます。
沖縄には7つの土帝君があるといわれ、その中でも船に乗って最初に辿り着いて祀られたところが、小禄の大嶺なのだとか。
小禄は歴史の古い土地といわれますが、しかしその多くは先の戦争で原形を失ってしまいました。
大嶺岬も大嶺の集落も、旧日本軍に接収され、戦後は米軍に、そして現在では航空自衛隊那覇基地と那覇空港として国有地化され、故郷での暮らしは無くなってしまいました。故郷の先祖が祀られ地域を護ってきた聖地への御拝(お参りともいえる)も許可書無くしては入れないといいます。

旧暦の5月4日(ユッカノヒー)には、現在の集落にある御嶽で御願バーリーを行い、この御嶽を遙拝して故郷へとウトゥーシ(通し)、区民の健康と豊漁祈願を行っているのでした。

白い砂浜はありませんが、大嶺の地バーリーを大嶺自治会の公民館で再現しています。
「大嶺はもともと半農半漁でやってまいりましたので、一番残したいのはハーリーではないかと私はそう思っております」と、『大嶺の地バーリー』を長年継承され続けてきた赤嶺清徳さん。古里の魂はこの伝統芸能の中に息づいているのでしょう。

「観られなかった人たちへと、船を担いできて『地バーリー』を行ってきた先人たちのその思いやりの心と、力強い伝統行事を後世に残せるよう頑張ります」と、
地バーリー保存会からの宣言は、近くて遠くなってしまった故郷へと響き届いたことでしょう。
※取材協力:字大嶺自治会、地バーリー保存会、上原清様
(文+撮影:KUWAこと桑村ヒロシ)
【ryuQ最新記事】
今月のryuQプレゼント!!
プレゼント情報をもっと見る>>
今月のryuQプレゼント!!
プレゼントの応募は下記の応募フォームからご応募ください。
※酒類のプレゼントへの応募は20歳未満の方はご応募できません。
応募フォームはこちらから
ryuQは携帯からでも閲覧できます!!

ブログランキング【くつろぐ】
ランキングはこちらをクリック!
人気ブログランキング【ブログの殿堂】
にほんブログ村 沖縄情報
この記事へのコメント
ありがとうございます。
ご近所です、字大嶺。…といっても取材されたとおり
>現在では航空自衛隊那覇基地と那覇空港として国有地化され
なので戦後住んでいる地域のご近所ですが…。
地バーリーをやってる(やっていた)なんて知りませんでした。
こういう情報の提供って、暖かくて、ありがたいですね。
ご先祖様、おじいさんおばあさん、おじさんおばさん、子供たち…
大切にしたいですね。
ご近所です、字大嶺。…といっても取材されたとおり
>現在では航空自衛隊那覇基地と那覇空港として国有地化され
なので戦後住んでいる地域のご近所ですが…。
地バーリーをやってる(やっていた)なんて知りませんでした。
こういう情報の提供って、暖かくて、ありがたいですね。
ご先祖様、おじいさんおばあさん、おじさんおばさん、子供たち…
大切にしたいですね。
Posted by うっちら at 2007年06月19日 10:14
うっちらさん>
コメントありがとうございます。
今もしっかりと受け継がれているようですよ。
特別なアナウンスはなかったかもしれませんが
“アンテナ”が働き、導かれるように辿り着きました^^
またこれからも独自の取材を続けてゆきますので
応援お願いいたします!
うっちらさんの区でも、とりあげてほしい地域情報などありましたら
ぜひ、遠慮無くお声をかけてくださいね。
それでは、これからもよろしくお願いします☆
コメントありがとうございます。
今もしっかりと受け継がれているようですよ。
特別なアナウンスはなかったかもしれませんが
“アンテナ”が働き、導かれるように辿り着きました^^
またこれからも独自の取材を続けてゆきますので
応援お願いいたします!
うっちらさんの区でも、とりあげてほしい地域情報などありましたら
ぜひ、遠慮無くお声をかけてくださいね。
それでは、これからもよろしくお願いします☆
Posted by KUWA at 2007年06月19日 10:52
ハイサイKUWAさん。
先日は偶然にもお会いできて嬉しかったです(^^v
地バーリーの行事は知っていたのですが
見るのは初めてでした。
保存会のメンバーに中学の先輩がいて
取材に来いと、ビール2~3本で承諾!!
次回は、ご一緒に参加しましょうね
ところで「旧大嶺集落の精密模型」を
参考にご覧下さいませ。
http://takara.ne.jp/oomine/mokei.html
先日は偶然にもお会いできて嬉しかったです(^^v
地バーリーの行事は知っていたのですが
見るのは初めてでした。
保存会のメンバーに中学の先輩がいて
取材に来いと、ビール2~3本で承諾!!
次回は、ご一緒に参加しましょうね
ところで「旧大嶺集落の精密模型」を
参考にご覧下さいませ。
http://takara.ne.jp/oomine/mokei.html
Posted by oroku at 2007年06月19日 12:34
orokuさん>
どうもこんにちは。
先日はどうもありがとうございました。
『地バーリー』を拝見させて頂ける機会に恵まれ、
そしてまた、こうやってご紹介させて頂く機会を頂き、
大嶺地区の皆様、関係者の皆様、ありがとうございました。
また、orokuさんともようやくお会いでき、感謝です。
まだお会いしたことが無かったのに、
なぜかすぐ、orokuさんだ、と気づきました^^
あとで、お声をかけさせて頂くことができ、
ようやく、つながりました。
orokuさんからお知らせ頂いた、旧大嶺地区の模型の記事、
これから拝見させて頂きますね。
ご紹介ありがとうございます。
また今後とも、どうぞよろしくお願いいたします!
どうもこんにちは。
先日はどうもありがとうございました。
『地バーリー』を拝見させて頂ける機会に恵まれ、
そしてまた、こうやってご紹介させて頂く機会を頂き、
大嶺地区の皆様、関係者の皆様、ありがとうございました。
また、orokuさんともようやくお会いでき、感謝です。
まだお会いしたことが無かったのに、
なぜかすぐ、orokuさんだ、と気づきました^^
あとで、お声をかけさせて頂くことができ、
ようやく、つながりました。
orokuさんからお知らせ頂いた、旧大嶺地区の模型の記事、
これから拝見させて頂きますね。
ご紹介ありがとうございます。
また今後とも、どうぞよろしくお願いいたします!
Posted by KUWA at 2007年06月19日 13:29
大嶺の地バーリー(ぢばーりー)
知りませんでした・・・
何か興味をそそられました・・・
知りませんでした・・・
何か興味をそそられました・・・
Posted by 風人 at 2007年06月19日 13:34
風人さん>
いつか、那覇ハーリーの国際通りパレードなどで、
大嶺の地バーリーも、お披露目されると素晴らしいかも、と思いました。
あくまでも伝統に沿った行事でありましょうから、
そういう機会が訪れるかどうかはわからないところでありますが、
那覇ハーリーともまったく無縁ではないようなので、
例えばそういう機会に、ぜひ大嶺地区の歴史などを、
多くの人に知ってもらえる機会もできるのではないかな、とも思いました。
その前にまずは大嶺地区の伝統行事についてのこのような記事を通して、
“忘れてはならないもの”に、また少しでも触れて頂けたらと思います。
いつか、那覇ハーリーの国際通りパレードなどで、
大嶺の地バーリーも、お披露目されると素晴らしいかも、と思いました。
あくまでも伝統に沿った行事でありましょうから、
そういう機会が訪れるかどうかはわからないところでありますが、
那覇ハーリーともまったく無縁ではないようなので、
例えばそういう機会に、ぜひ大嶺地区の歴史などを、
多くの人に知ってもらえる機会もできるのではないかな、とも思いました。
その前にまずは大嶺地区の伝統行事についてのこのような記事を通して、
“忘れてはならないもの”に、また少しでも触れて頂けたらと思います。
Posted by KUWA at 2007年06月19日 13:43
地域の伝統「地バーリー」素敵です。歌の内容が知りたいたいです!!
調べるなら県立図書館ですか?
調べるなら県立図書館ですか?
Posted by kanepan99 at 2007年12月27日 15:47
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
てぃーだな特集新着記事
お気に入り
QRコード
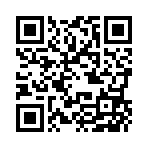
読者登録(更新のお知らせ通知)
アクセスカウンタ
ryuQ特集記事>検索
バックナンバー
ryuQプロフィール
ryuQ編集室
カテゴリー
観光・レジャー (70)
グルメ (29)
ビューティー (6)
アウトドア・スポーツ (3)
エンターテイメント (6)
沖縄の芸能・文化 (36)
ビジネススタイル (1)
暮し生活 (41)
趣味・遊び・お得 (100)
健康・医療 (3)
沖縄の人々 (196)
ペット・アニマル (12)
沖縄の匠 (10)
THE泡盛 (14)
壁紙 (57)
ショップ紹介 (29)
三線 (15)
ECOライフ (8)
戦争と平和 (16)
スピリチュアル (11)
沖縄のスポーツ (11)
CD新譜情報 (35)
映画情報 (23)
南島詩人・平田大一『シマとの対話』 (75)
ryuQ編集部から (4)
琉球百科シリーズ (163)
エイサー (10)
写真でみる沖縄 (7)
新製品情報 (8)
過去記事・月別に表示





















