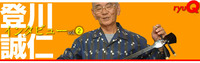大工哲弘のガムラン‐ユンタ【前編】

「音楽に国境はある。それを越境していくのが音楽家たちだ」と語る大工哲弘氏は、今回八重山民謡とガムランとの競演を実現! 青年の頃からジャンルを越えて音楽と文化の交流を続けてきた氏だからこそ発言できる言葉ひとつひとつに、また大切なメッセージが込められていました。
 ——ニューアルバム『ガムラン‐ユンタ』は、なんと八重山民謡とガムランという意外な組み合わせですね!
——ニューアルバム『ガムラン‐ユンタ』は、なんと八重山民謡とガムランという意外な組み合わせですね!大工哲弘:意外なだけでなく「案外ぴったり合うね!」という声も結構多かったですよ。
(ぜひみなさん、お聴きになってみてください。)
——音楽のほかにも共通点などありましたか?
大工哲弘:大いにありますね。むしろ、我々の芸能の故郷はガムランなどにもあるのではないかと思うほど、舞踊での“指の使い”“足の運び”など、八重山のアブジャーマーをみているかのようなバリスダンスという踊りもありましたしね。

あと、バリ島の芸能のほとんどが寺院でされているんですね。それは“神様と芸能”と民衆の魂が一つになっているんだなということと、そういった敬虔な場所で芸能をやることがすごく新鮮に映ってきましたね。
それと、我々が育ってきた八重山の祭りでも、奉納芸能を御嶽(ウタキ)でやるわけです。そこから芸能は昇華していったことが、元々の原点だと思うんです。

——集落の生活のなかで、それぞれの地域を護ってくださっている御嶽へ奉納芸能を収めるのが祭り。それが八重山もバリも共通していると。
大工哲弘:バリでは寺院が2キロおきくらいにあって、各寺院を核にして集落の芸能が毎日のように盛んに行われています。夜になるとどこの寺院も観光客がいっぱい集まっているんですよね。
 しかも演じているのが音楽を職業としている人たちでなく、そこに暮らす集落の人たちなんですよね。みんな小さい頃から修練を積み重ねてきた方達です。そうやって、街中が活気づいているんですよね。
しかも演じているのが音楽を職業としている人たちでなく、そこに暮らす集落の人たちなんですよね。みんな小さい頃から修練を積み重ねてきた方達です。そうやって、街中が活気づいているんですよね。そういった意味では、沖縄の観光産業もバリから学ぶものがたくさんあるのではないかと思うんですよね。
ただ立派な施設でやっているものが“これが沖縄の伝統芸能だ”というのは、何か違うと思う。やっぱり、屋根をとっぱらって天と通じ合えるところに、沖縄の民俗芸能があると思うんですよね。宮廷舞踊は別としても、それも元々は御庭(うなー)で行われていたというからやはり屋外のものであったのではないかと。ですから、どんどん野外に出て開かれるべきではないかと思うんです。
——ガムランの会場は寺院だったとのことですが、演奏そのものは屋外でされていたんですね?
大工哲弘:屋根はありませんでしたし、青銅の響きがどこまでも響くような心地よさがあって、本当に天まで届いて聴こえているんじゃないかと思うほどでしたよ。
 ——八重山も沖縄の芸能も、元々はマイクなどは使わず、生の歌声と三線や太鼓だけで聴かせていたのですよね?
——八重山も沖縄の芸能も、元々はマイクなどは使わず、生の歌声と三線や太鼓だけで聴かせていたのですよね?大工哲弘:そうなんですよ。僕らが高校の頃まで生年祝いの行事とか自宅でやっていたので、三線の地謡さんたちもみんな生でやっていましたね。
——国立劇場おきなわにしても生演奏で響き渡るような構造で作られているそうですけど、ほとんどの舞台がマイクを通した演奏になっていますね。
大工哲弘:実は、パレット市民劇場のオープニング公演でもマイク無しでやった事があるんですよ。ですが、後方で演奏する方々には聞こえにくいということでそれ以降はマイクを使ってやりましたね。また、南城市佐敷のシュガーホールもそういった構造のはずですが、やはりマイクを使わなければならないとのことで指示通りにした事もありましたよ。
それは現代の演者さんたちもマイクやモニタースピーカーがあって当たり前の環境にいて、小さな頃から生音での舞台に慣れていないというところもあると思うんです。
ですから、歌い手の発声法にしても、マイクありきの歌になってきていると思いますね。
——そういったことも全部含めて、バリでは芸能の原風景を見たような感じだったのですね?
大工哲弘:そうですね、タイムスリップしたようでした。環境にしても、田園風景が残っていたりとか。芸能では、“あっ、これは八重山のユンタだ”と思えるようなものがありましたしね。たくさんの音楽がありました。
実は、僕の舞台『ゆんたしょーら』もバリにならったものがあるんですよ。

——そうだったんですか!
大工哲弘:とくに後半のユンタの部分はそうですね。例えば、みんなで揃って手拍子を打つのは、バリでいえばケチャですね。太鼓さえも使わずに、楽器なしで人の手のみで拍子を響かせるのはなんて素晴らしいのだろうと。
 ——先ほど、バリのガムラン奏者は皆、集落の方々だとおっしゃっていましたが、八重山の村々の芸能にしてもそうですよね。ですが、八重山もバリも一般の方々とはいっても、小さい頃からその祭祀を観て体験してきて修練を積まれてきた方々だということが大事なポイントですよね。
——先ほど、バリのガムラン奏者は皆、集落の方々だとおっしゃっていましたが、八重山の村々の芸能にしてもそうですよね。ですが、八重山もバリも一般の方々とはいっても、小さい頃からその祭祀を観て体験してきて修練を積まれてきた方々だということが大事なポイントですよね。大工哲弘:バリのほうでも、沖縄でいう公民館のような集会所が各集落にあるんですよ。そこでは地域の子供たちもガムランを習っているんですね。もうひとつは婦人会のガムランまであったり。もちろん、集落代表のガムランもあるわけで、いつもガムランの音が聞こえてくるくらいに修練とその積み重ね、層の厚さがしっかりとあるところが魅力的ですし、それでいて昼間はみんなそれぞれほかの職業を持っていて、そうやって生活の中に文化があるというのが素敵だなと思いましたね。
かつての八重山のユンタと同じです。バリのそういうところにとても共感できました。

——また八重山と共通の文化で、バリにも凧揚げがあるそうですね。それも日常的なのだとか?
大工哲弘:伝統的な凧揚げは石垣にもありますが、バリでもよく凧が空にあがっていましたね。どこの家でも飛ばしていましたけど、考えてみれば今沖縄で同じ事をしようとしても無理ですよね。

——電線に引っかかったり、低空飛行している戦闘機に引っかかるかもしれませんものね。
大工哲弘:バリでは1970年以降は、景観を守るため“ヤシの木以上の建物は建ててはならない”という制限をつけたりとかしているわけで。
沖縄でもやっとようやく最近になって、竹富島で“売らない買わない壊さない”とか、首里でも景観を守る整備をし始めましたね。

大事なものが残っているからこそ、そこに“故郷に帰ってきた”と思えるようなものが感じられるんだ、ということですね。
(スペシャルインタビュー【後編】につづく)
(取材: 桑村ヒロシ)
【ryuQ最新記事】
今月のryuQプレゼント!!
プレゼント情報をもっと見る>>
今月のryuQプレゼント!!
プレゼントの応募は下記の応募フォームからご応募ください。
※酒類のプレゼントへの応募は20歳未満の方はご応募できません。
応募フォームはこちらから
ryuQは携帯からでも閲覧できます!!

ブログランキング【くつろぐ】
ランキングはこちらをクリック!
人気ブログランキング【ブログの殿堂】
にほんブログ村 沖縄情報
てぃーだな特集新着記事
お気に入り
QRコード
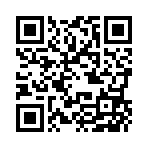
読者登録(更新のお知らせ通知)
アクセスカウンタ
ryuQ特集記事>検索
バックナンバー
ryuQプロフィール
ryuQ編集室
カテゴリー
観光・レジャー (70)
グルメ (29)
ビューティー (6)
アウトドア・スポーツ (3)
エンターテイメント (6)
沖縄の芸能・文化 (36)
ビジネススタイル (1)
暮し生活 (41)
趣味・遊び・お得 (100)
健康・医療 (3)
沖縄の人々 (196)
ペット・アニマル (12)
沖縄の匠 (10)
THE泡盛 (14)
壁紙 (57)
ショップ紹介 (29)
三線 (15)
ECOライフ (8)
戦争と平和 (16)
スピリチュアル (11)
沖縄のスポーツ (11)
CD新譜情報 (35)
映画情報 (23)
南島詩人・平田大一『シマとの対話』 (75)
ryuQ編集部から (4)
琉球百科シリーズ (163)
エイサー (10)
写真でみる沖縄 (7)
新製品情報 (8)
過去記事・月別に表示