映画の秋に『沖縄劇映画大全』『アンヤタサ!』ほか
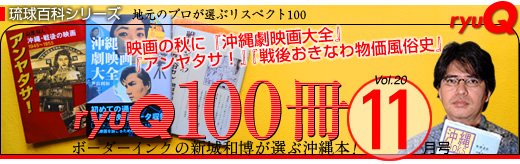
今回は、映画の話。いやもちろん映画にまつわる沖縄県産本のことである。
 実はこの秋ボーダーインクの新刊として『沖縄劇映画大全』(世良利和著)が出た。僕が編集を担当した本ではないので、出来上がるのを楽しみにしていたのだ。
実はこの秋ボーダーインクの新刊として『沖縄劇映画大全』(世良利和著)が出た。僕が編集を担当した本ではないので、出来上がるのを楽しみにしていたのだ。 これは、戦前の黎明期の作品から、戦後、そして現在までの作品を、その内容や監督や出演者など、作品に関する様々なデータを網羅した、〈沖縄映画〉のデータベースとなる本である。それだけでなく、多分初めてだろうが、その戦前戦後、現在までの〈沖縄映画〉の歴史を語る通史「沖縄映画略史」も収録されている。これは略史と銘打っているが力作である。これだけで一冊の本の内容がある。帯の文句にあるように「沖縄映画を論じるための〈基礎〉となる一冊」だと言える。
著者は、岡山在住の映画研究者で、もともとドイツ映画や松田優作などの研究をしていた方。岡山から沖縄に十年通ってまとめた「大全」と銘打つにふさわしい時間が掛かっているのだ。
さて〈沖縄映画〉という定義は難しいのだが、ここでは「何らかの意味で沖縄がテーマや舞台、あるいは物語の背景となっている作品」と、きわめて大きくとらえている。なので、紹介されている作品の数も半端じゃない。多分500ちかくの作品を取り上げている。戦前の作品の多くは現存していないのだが、著者は、当時の模様を語った文献や新聞記事などをもとに推定したり、また幻とされていた作品を発見したりして、よくぞここまで調べたものだと感心するしかない。当然作品の多くは実際著者が観て内容を記述している。そういう意味では、データだけではなく、映画評としても読めるところがまたおもしろい。特に最近の「沖縄映画」に関しての辛口の批評は、ニヤリとさせらた。最近の「沖縄映画」とは……。
〈……ロケは那覇市など沖縄本島中・南部を中心に行われ、それらをつないだ「架空の沖縄」が舞台として設定されている。中心となる役を本土の俳優が演じ、脇に沖縄の役者を配して地元色を出すというやり方も含め、現在の『沖縄映画ブーム』のスタイルを代表する作品だ。〉
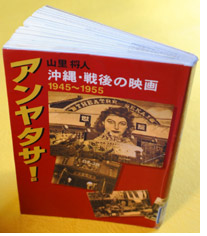 これは少し前に公開されたある沖縄映画に対するものだが、こういう風潮の、実は敢えて沖縄を舞台にしないでもいいテーマの映画を、著者は「沖縄映画略史」の中で〈名前のない沖縄〉と述べている。これは映画だけでなく、沖縄を表現する、そして考える上で覚えておきたい視点だろう。
これは少し前に公開されたある沖縄映画に対するものだが、こういう風潮の、実は敢えて沖縄を舞台にしないでもいいテーマの映画を、著者は「沖縄映画略史」の中で〈名前のない沖縄〉と述べている。これは映画だけでなく、沖縄を表現する、そして考える上で覚えておきたい視点だろう。
県産本では、映画に関する本というのは少なくて、ニライ社が2001年に出した『アンヤタサ!—戦後・沖縄の映画1945‐1955 』(山里将人著)くらいしかぱっとは思い浮かばない。著者は本職のお医者さんというよりも、熱狂的な映画マニアとして有名だ。戦後の沖縄での映画興行について、びっくり仰天エピソード満載の一冊。一種の戦後沖縄世相史である。「アンヤタサ!」とは、「そうだったな!」という意味。これもまた沖縄で映画を語る上で欠かせない県産本だろう。……実は手にしたことはあっても読んだことなかったのだが、これを機会に俄然読みたくなった本である。最近出たノン・フィクション作家佐野眞一の『沖縄 誰にも書かれたくなかった戦後史』のネタ本のひとつでもあるし。
 〈恐らく、沖縄で後にも先にも私ほど長く映画を愛し、映画に関わり、趣味の域を超え、道楽し、持続するつらさ故に楽が欠け、ひたすら無限の「道」を歩み続けた者はいないだろう〉(「あとがき」より)
〈恐らく、沖縄で後にも先にも私ほど長く映画を愛し、映画に関わり、趣味の域を超え、道楽し、持続するつらさ故に楽が欠け、ひたすら無限の「道」を歩み続けた者はいないだろう〉(「あとがき」より)
世相史で思い出したが、1987に出た『戦後おきなわ物価風俗史』(琉球新報社会部編 沖縄出版)の中にも、沖縄の映画館事情が触れられていた。この本は、戦後の沖縄を様々なものの「物価」の変遷を通してみる、という新聞連載をまとめたもの。理容料金、おふろ屋さん、洋裁学校、バス、沖縄ソバ、アイスクリーム、ポークランチョンミート、塩、ステーキ、煙草、コーラ、保育料、プロパンガス、グルクンなどなど、いろんなものが取り上げられている。映画に関しては「貧しい時代のココロの糧」と題して、戦後の最盛期には221館も映画館が沖縄にあった頃の映画料金は「40円」。あっ、単位は「B円」です。ドルの頃は1958年で35セント、67年ころには1ドルだった。ちなみに沖縄そばは、1959年頃で20〜25セントである。
記録に残しておくということは大切なことで、大変なことだなぁと、つれづれなるままに紹介した本をみてそう思った、秋の日でした……。
●新城和博の『ryuQ100冊』バックナンバー:
http://ryuq100.ti-da.net/c73391.html

プロフィール:新城和博(しんじょうかずひろ)
沖縄県産本編集者。1963年生まれ、那覇出身。編集者として沖縄の出版社ボーダーインクに勤務しつつ、沖縄関係のコラムをもろもろ執筆。著者に「うっちん党宣言」「道ゆらり」(ボーダーインク刊)など。
ボーダーインクHP:http://www.borderink.com/
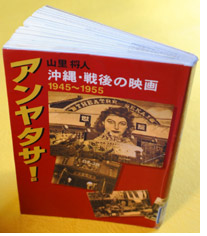 これは少し前に公開されたある沖縄映画に対するものだが、こういう風潮の、実は敢えて沖縄を舞台にしないでもいいテーマの映画を、著者は「沖縄映画略史」の中で〈名前のない沖縄〉と述べている。これは映画だけでなく、沖縄を表現する、そして考える上で覚えておきたい視点だろう。
これは少し前に公開されたある沖縄映画に対するものだが、こういう風潮の、実は敢えて沖縄を舞台にしないでもいいテーマの映画を、著者は「沖縄映画略史」の中で〈名前のない沖縄〉と述べている。これは映画だけでなく、沖縄を表現する、そして考える上で覚えておきたい視点だろう。 県産本では、映画に関する本というのは少なくて、ニライ社が2001年に出した『アンヤタサ!—戦後・沖縄の映画1945‐1955 』(山里将人著)くらいしかぱっとは思い浮かばない。著者は本職のお医者さんというよりも、熱狂的な映画マニアとして有名だ。戦後の沖縄での映画興行について、びっくり仰天エピソード満載の一冊。一種の戦後沖縄世相史である。「アンヤタサ!」とは、「そうだったな!」という意味。これもまた沖縄で映画を語る上で欠かせない県産本だろう。……実は手にしたことはあっても読んだことなかったのだが、これを機会に俄然読みたくなった本である。最近出たノン・フィクション作家佐野眞一の『沖縄 誰にも書かれたくなかった戦後史』のネタ本のひとつでもあるし。
 〈恐らく、沖縄で後にも先にも私ほど長く映画を愛し、映画に関わり、趣味の域を超え、道楽し、持続するつらさ故に楽が欠け、ひたすら無限の「道」を歩み続けた者はいないだろう〉(「あとがき」より)
〈恐らく、沖縄で後にも先にも私ほど長く映画を愛し、映画に関わり、趣味の域を超え、道楽し、持続するつらさ故に楽が欠け、ひたすら無限の「道」を歩み続けた者はいないだろう〉(「あとがき」より) 世相史で思い出したが、1987に出た『戦後おきなわ物価風俗史』(琉球新報社会部編 沖縄出版)の中にも、沖縄の映画館事情が触れられていた。この本は、戦後の沖縄を様々なものの「物価」の変遷を通してみる、という新聞連載をまとめたもの。理容料金、おふろ屋さん、洋裁学校、バス、沖縄ソバ、アイスクリーム、ポークランチョンミート、塩、ステーキ、煙草、コーラ、保育料、プロパンガス、グルクンなどなど、いろんなものが取り上げられている。映画に関しては「貧しい時代のココロの糧」と題して、戦後の最盛期には221館も映画館が沖縄にあった頃の映画料金は「40円」。あっ、単位は「B円」です。ドルの頃は1958年で35セント、67年ころには1ドルだった。ちなみに沖縄そばは、1959年頃で20〜25セントである。
記録に残しておくということは大切なことで、大変なことだなぁと、つれづれなるままに紹介した本をみてそう思った、秋の日でした……。
●新城和博の『ryuQ100冊』バックナンバー:
http://ryuq100.ti-da.net/c73391.html

プロフィール:新城和博(しんじょうかずひろ)
沖縄県産本編集者。1963年生まれ、那覇出身。編集者として沖縄の出版社ボーダーインクに勤務しつつ、沖縄関係のコラムをもろもろ執筆。著者に「うっちん党宣言」「道ゆらり」(ボーダーインク刊)など。
ボーダーインクHP:http://www.borderink.com/
【ryuQ最新記事】
今月のryuQプレゼント!!
プレゼント情報をもっと見る>>
今月のryuQプレゼント!!
プレゼントの応募は下記の応募フォームからご応募ください。
※酒類のプレゼントへの応募は20歳未満の方はご応募できません。
応募フォームはこちらから
ryuQは携帯からでも閲覧できます!!

ブログランキング【くつろぐ】
ランキングはこちらをクリック!
人気ブログランキング【ブログの殿堂】
にほんブログ村 沖縄情報
てぃーだな特集新着記事
お気に入り
QRコード
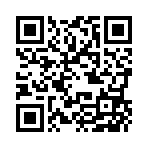
読者登録(更新のお知らせ通知)
アクセスカウンタ
ryuQ特集記事>検索
バックナンバー
ryuQプロフィール
ryuQ編集室
カテゴリー
観光・レジャー (70)
グルメ (29)
ビューティー (6)
アウトドア・スポーツ (3)
エンターテイメント (6)
沖縄の芸能・文化 (36)
ビジネススタイル (1)
暮し生活 (41)
趣味・遊び・お得 (100)
健康・医療 (3)
沖縄の人々 (196)
ペット・アニマル (12)
沖縄の匠 (10)
THE泡盛 (14)
壁紙 (57)
ショップ紹介 (29)
三線 (15)
ECOライフ (8)
戦争と平和 (16)
スピリチュアル (11)
沖縄のスポーツ (11)
CD新譜情報 (35)
映画情報 (23)
南島詩人・平田大一『シマとの対話』 (75)
ryuQ編集部から (4)
琉球百科シリーズ (163)
エイサー (10)
写真でみる沖縄 (7)
新製品情報 (8)
過去記事・月別に表示


















